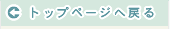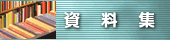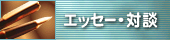地域処遇の課題は「医療観察法」最大の隘路(あいろ)として残る
Community-based treatment as a deadlock of the Treatment
of Mentally Disordered Offenders Act
岡崎伸郎(精神科医)
2008年3月
はじめに
2005年7月に「心神喪失者等医療観察法」(以後、医療観察法ないし本法と略)が施行されてからすでに2年を超えた。検察官による本法申立て件数は、2007年7月末までの約2年間で755人(不起訴処分に基づく申立て654人、確定裁判に基づく申立て101人)であり、ほぼ1日に1人という割合で推移している。施行当初は、足並みのそろわない法解釈や準備不足による混乱が各地に散見されたが、ある程度の経験が積み上げられた本稿執筆時(2007年秋)においては、導入期特有の混乱が徐々に収束に向かう一方、本法そのものが内包する問題点がいよいよあらわになってきているようにも思われる。
本稿では、保護観察所の機能と権限の限界、強制処遇的側面と保健福祉サービス的側面の区別、精神保健福祉法との二重基準的運用の問題、対象者に関する情報共有のあり方、などに言及しながら、本法の地域処遇をめぐって現場に生じている困難な状況を概観する。これよって、制度運用の技術的洗練といったレベルでは解決できない本法の本質的課題が浮かび上がってこよう。
1.地域処遇に関する議論の低調を憂える
医療観察法についてはすでにおびただしい議論がなされてきた。しかしそれらは、鑑定入院、審判、指定入院機関における医療といった、形はどうあれ対象者の身柄が確保されている段階での諸問題に集中するきらいがあった。それに比べると、地域処遇についての議論は極めて低調のまま今日に至っている。たとえば、本学会第2回大会(2006)では、一般演題19題の中で本法の地域処遇をテーマとしたものはなく、シンポジウムの中で蛯原 1)が社会復帰調整官(本法施行時には法務省保護局精神保健観察企画官)の立場からこの問題を論じたにすぎない。また、本稿の元になるシンポジウムが開催された本学会第3回大会(2007)でも、一般演題32題の中で本法の地域処遇を直接のテーマとしたものは見当たらない。
議論が低調な理由はいくつか考えられる。
本法対象者の大半が入院処遇から始まるだろうから、地域に多くの対象者が戻ってくるまでには多少の準備期間があると国も関係者も当初予測していたことは大きい。また、社会復帰調整官や支援にかかわる地方自治体職員のなかでは、学会などの公器を活用する習慣が精神科医ほどには定着していないという背景も無視できない。さらには、地域社会に衆知の事件と関係している場合には対象者が特定されやすいため、本格的なケーススタディがしにくいという事情も大きく影響していると思われる。
しかし、このような周辺事情を尻目に、地方裁判所の当初審判の結果は大方の予想に反して、2007年7月末までの決定合計667件のうち、入院決定381件(57%)、通院決定145件(22%)、本法の医療を行わない決定123件(18%)、申立て却下18件(3%)となっており、最初から通院処遇というケースが相当の割合にのぼっている。これらにおいては調整期間のなさゆえにさまざまな混乱が生じている。一方、入院処遇から開始した対象者も、今後続々と地域処遇へと移行していくのであるから、地域処遇問題はすでに量的にも喫緊の課題であるといえよう。
筆者は施行前から、本法の運用における最大の難関は地域処遇であると主張してきた2)。しかも、困難の多くが制度の根幹部分の欠陥によっているために、運用技術の洗練といったレベルによる解決は期待薄であると考えている。そもそも鍵も塀もない茫洋とした「地域」というフィールドでの、国家命令による医療や処遇(精神保健観察)という強制システムを前向きにイメージすることが、筆者にはどうしてもできない。
一方で医療観察法は、その第一義的目的として、対象者の地域社会への復帰を掲げている。それが本格的に問題となるのは、もちろん地域処遇の段階である。いったい本法の地域処遇システムは、対象者の社会復帰にとって有効なのか。そのことが立法の趣旨に照らして常に問われているということになる。したがって、地域処遇に関する議論の低調は、きわめて憂慮すべき事態と言わざるを得ないのである。その意味で、本学会が今回初めて地域処遇に焦点を当てたシンポジウムを開催したのは、時宜を得た企画と言えよう。
2.地域処遇の課題
紙幅の関係上、地域処遇における課題のすべてを詳細に論じることはできないので、項目立てして簡単に整理しておく。
a.指定通院医療機関の不十分な体制
量的、質的、また地域バランスの観点からも、圧倒的に不十分な現状は覆うべくもない。一般精神医療のモデルとなるような質の高さを当初は謳いながらも、実際には指定通院医療機関が少ないためほとんど選択の余地がなく、したがって居住地の選定も通院可能かどうかという条件にばかり左右されること、救急への応需体制が整わないことなど、社会復帰阻害因子が目立つ。医療機関にとって指定を受ける経済的メリットに乏しいことも、整備の遅れを助長させており、また指定されていても、さまざまの理由で実際の事例引き受けに難色を示す場合が多くなっている。
b.住居確保の困難
これが最も困難な課題となるであろうことは、法施行前からしばしば指摘されていた。殺人や自宅放火といった地域社会を震撼させた事件であればあるほど、対象者が元の居住地に戻ることは難しくなる。かといって未知の土地のグループホームや民間アパートを自力で捜せるはずもない。そこで「住居確保の目途が立たないためやむを得ず指定入院医療から開始する」という、法の趣旨に反する審判が横行するのではないかと危惧する声があった。そこでこれを避けるための現実的対応として「医療観察法では通院処遇だが、とりあえず精神保健福祉法による入院(医療保護入院や任意入院)をさせて、その間に地域移行への調整をする」というやり方が常套手段になりつつある。これは医療観察法にも精神保健福祉法にも抵触しないものの、本来なら入院していなくてよい人が地域の受け皿がないために入院を余儀なくされる、という意味で「社会的入院」そのものであるから、対象者の社会復帰促進という法の理念から遠く隔たった運用との批判を免れない。特定の生活訓練施設が、とりあえずの退院先として偏って利用される事態も生じている。
このように、先端的精神科医療のモデルとなるはずの本法制度が、旧来の精神科医療の構造的問題すら乗り越えられないことを露呈する結果となっているのである。
c.保護観察所の機能と権限の限界
地域処遇は、指定通院医療機関、都道府県(保健所など)、市町村、精神保健福祉センター、社会復帰施設など、多くの関係機関の連携のもとに進められる。そこで全体の要(かなめ)になるのが保護観察所の社会復帰調整官とされている。ところが要といっても、単なる調整役にとどまるのか、司令塔の役割を果たすのか、また対象者への直接対応にオンコール体制を敷いて責任を持つのかといったことが、今もって不明確である。法施行時に、各都道府県(政令市を含む)と保護観察所との間に「地域処遇運営要領」が取り交わされているが、それらのいくつかをみても、「連携」や「協力」ばかりが強調されて、責任分掌についての取り決めが少ない。実際に各保護観察所の動きもマチマチであり、個々の社会復帰調整官の力量や業務量(担当ケースの数)に大きく左右されている印象をぬぐえない。
また本法の地域処遇は、対象者の社会復帰を目的に掲げながらも国家の命令による強制処遇であることは紛れもない事実である。ところがこれを統括する保護観察所には、「調整」「見守り」「指導」の役割はあっても、何らの権限も強制力も与えられていない。そのため現実問題として精神保健観察を完遂できない局面が多々生じ得る。たとえば通院中断しかかったケース(緊急対応を要する病状悪化とは限らない)に、保護観察所が受診勧奨はできても受診命令はできないことになっているが、これは強制処遇制度として致命的な欠陥である。
d.強制処遇的側面と任意の保健福祉サービスの不明確
地域処遇計画については、対象者に懇切丁寧に説明し、可能な限り同意を得ることとされている。そのなかで、通院・服薬の遵守や社会復帰調整官からの連絡に応じること、転居や旅行について事前に届け出ることなどは、必ず守られなければならない事項である。これに対して、デイケアや社会復帰施設の利用などは、本来任意のものであって、勧めることはできても強制はできない。ところが対象者への説明において、どこまでが義務でどこからが推奨なのかといった区別が曖昧になされていることが多い。これは重大な誤解やトラブルにつながりかねない。
e.精神保健福祉法との使い分けの問題
特に病状悪化時の緊急対応として、決定までに時間のかかる医療観察法の再入院申立てではなく、まず精神保健福祉法の入院(措置入院、医療保護入院、任意入院を含む)を活用する方針を国は示している。これは現実的運用のようにも見えるが、法理にかなっているのか疑義もある。本法の再入院要件と精神保健福祉法の「他害のおそれ」要件とのダブルスタンダード問題が整理されないままであり、現場は極めて難しい判断を強いられる。
またたとえば、措置入院や移送制度など精神保健福祉法で臨むことになれば、社会復帰調整官が直接関わる法的根拠がなくなってしまうが、だからといって地方自治体職員に緊急時の対応をすべて任せてしまうのかどうかもまったく不明である。
f.地域住民を含む情報共有のあり方
次節で述べる。
3.地域処遇制度は社会復帰に有効なのか
本法の目的に掲げられた「対象者の地域社会への復帰」という観点から、地域処遇ガイドラインを読み直してみると、総論の最後に触れられている「地域住民等への配慮」は、これまで議論されたことの少ない部分だが、重要なポイントであると考える。
過去に地域社会を騒がせた対象者が、時間をかけながら再びそこに受け入れられ、安定した生活を再建・維持できるようになることが社会復帰である。そのためには地域住民の理解と協力が不可欠である。この理念については誰も否定しないだろう。しかし、そのことの個別事例での実践は、本法成立以前に比べていっそう困難になってしまったという思いを禁じ得ない。この制度を誠実に運用しようとすればするほど、市民社会に対して恐ろしげな異形の制度として立ち現れるからである。法務省が社会復帰目的というソフトな顔によって本法を市民に定着させようとするなら、裁判員制度の普及に匹敵するような一大プロパガンダでも展開するしかなかろう。しかしそうしたところで、精神障害者一般に対する偏見の解消や社会参加の促進という普遍的課題を一方に置いた場合のバランスの悪さがあまりにも際立つ。
さて、地域処遇ガイドラインは、個別事例ごとの「地域住民等への配慮」について具体的に何を提唱しているのか。以下に、関連する箇所を引用する。
個別の事情に応じ、一定の範囲で地域住民に情報を提供することで、対象者の社会復帰が促進されると見込まれる場合には、対象者の個人情報については厳に慎重に取り扱わなければならないことに留意しつつ、対象者の同意に基づき、地域住民に提供可能な情報の範囲を定めるものとする。被害者等についても、必要に応じ、対象者の社会復帰を促進する観点から、同様の配慮を行う。
これは非常に曖昧な文章であるが、よく読めばほとんど何も言っていないに等しいことが判る。地域住民に対して、いかなる場合にいかなる範囲の個人情報を提供するのが社会復帰促進的であるかについて、ガイドラインは全く見解を示さない。現場の慎重な判断に任せるというのである。対象者の社会復帰のために、場合によっては被害者に知らせた方がよい情報というのも、具体的にイメージすることが難しい。
このように空文に近いガイドラインであるが、それはいったんおいて、試みに、地域で第一線に立つ社会復帰調整官が、キーパーソンになりそうな一般市民、たとえば部屋を貸してくれそうな民間アパートの大家に対して、制度説明をしながら情報提供するという場面を考えてみる。「社会復帰」「調整」官としてはルーチンな業務であろう。ところが実際には、社会復帰調整官が名刺を渡して自らの職分を丁寧に説明すればするほど(それは制度説明でもあるが)、殺人・傷害・放火…といったまがまがしい出来事との関連に触れないわけにはいかず、その結果、現実社会の厚い壁を痛感するばかりとなろう。かといって、一般の精神保健福祉士とは異なって医療観察法の枠内で仕事をする社会復帰調整官が、曖昧な説明や“嘘も方便”を使うことは許されないから、困難を承知で正攻法によらざるをえない。筆者は、各地の社会復帰調整官の粉骨砕身に心から敬意を表する者であるが、それだけに特殊な制度の特殊な職分が邪魔をして身動きがとりにくくなることに、もどかしさを感じる。これは社会復帰調整官にとって気の毒という問題ではなく、彼の活動が制限されることは、彼を頼みとする対象者にとっての深刻な不利益を意味するので、ことは重大である。
それならばいっそのこと、社会復帰調整官は表舞台から一歩退いて、医療機関のケースワーカーや地方自治体の精神保健福祉相談員が住居探しなどに奔走するのがよいのだろうか。彼らの場合は医療観察法の枠内でケースワークをするわけではないので、事情をぼかすなど臨機応変に振る舞うこともある程度は許されよう。しかしそれは、本法が成立する前から不十分ながら脈々と行われてきたことであって、本法の使いにくさを従来システムで補うというにすぎない。
もう1つ例をあげる。筆者は、入院処遇から通院処遇への移行が近いケースで、退院後の生活訓練施設の利用についての事前協議に参加したことがある。その席で、施設のほかの入所者に対してどの程度まで事情説明すべきと考えるかを社会復帰調整官に訊ねた。ところが彼女は、こうした課題をまったく想定していないようであったため、協議が行き詰まったのである。そもそも社会復帰施設サイドにこうしたデリケートな判断を委ねるのは、無理がある。かといって、前述のように地域処遇ガイドラインは何も語らない…
こうした現場の実情を見るにつけ、医療観察法の地域処遇体制だからこそ対象者の社会復帰にとって大きなメリットがあるという心証を、筆者はどうしても持てないのである。
おわりに
重大な触法行為歴のある精神障害者の地域社会への復帰は、きれい事では済まされない世俗的難事業である。世間の風は、ひと通りの制度整備でしのげるほど暖かくないことが、法施行後の日々の経験から明らかになりつつある。現実的・世俗的観点から見て難しい課題であればあるほど、柔軟性やあいまいさを呑み込んだ経験知でしか解決できない、というのが世の理(ことわり)であるが、医療観察法にそのような成熟した懐の深さを望むことはできない。しかも本法の硬い性質上、制度に直接かかわる人と周辺にいる人との距離が広がる傾向を否めない。こうしたことは、地域社会への復帰という対象者が希求する目標にとって、重い足枷(あしかせ)となり続けるだろう。
従来のシステムを地道に手直しするのと比べて、医療観察法の導入が本当に進歩といえるのかどうか、われわれは真剣に問い直す時期に来ている。
出典
司法精神医学会誌 2008年3月 第3巻 第1号
文献
1)蛯原正敏:医療観察制度の現状と課題−社会復帰調整官の立場から−.司法精神医学,2(1):61-70,2007
2)岡崎伸郎:「医療観察法」による地域処遇は制度破綻を免れない.精神経誌,108(5):510-514,2006
Summary
心神喪失者等医療観察法にはさまざまの欠陥があるが、なかでも地域処遇の段階は多くの課題を抱える。しかもそれらは、運用技術の洗練というレベルでは解決できない制度そのものの根本的性質に起因している。本法制度特有の硬さは、本法の第一義的目的である「対象者の地域社会への復帰」にとって、阻害要因にならざるをえない。特に対象者の社会復帰に不可欠である地域社会の理解と協力という課題において、その困難が顕在化する。
従来のシステムを手直しするのと比べて、本法の導入が進歩と言えるのかどうか、根底から問い直す必要がある。
Key words
心神喪失者等医療観察法(the Treatment of Mentally Disordered Offenders Act),地域処遇(community-based treatment),社会復帰調整官(rehabilitation coordinator)
著者所属
小高赤坂病院 Odaka Akasaka Hospital
岡崎伸郎関連書籍
● 精神医療50号 /岡崎伸郎,『精神医療』編集委員会 編ー批評社,2008,5
精神医療2008 第49号次号予告より
精神医療 2008
次号予告 PSYCHIATRY 第50号記念特集号
総特集 医療制度改革の中の精神科医療
[責任編集]朝日俊弘+阿保純子+岡崎伸郎
本紙は創刊以来、地域精神科医療の現状分析とあるべき姿の模索というテーマを追い続けてきました。他の領域からの“周回遅れ”を自認してきた私たち精神科医療従事者や利用者にとって、精神科医療の特殊性と後進性をいかにして超克するかが、常に最大の関心事でした。
そうしている間にも、この国の保健・医療・(介護を含む)福祉をめぐる制度や施策は大きく変貌しました。特に2005年末に政府・与党が「医療制度改革大綱」を取りまとめて以来、その考え方に沿った一連の医療制度改革法が2006年に成立し、それらが段階的に施行されつつある今日までの情勢は、まさに激動にふさわしいものです。
変化を受けた制度や施策を法律の名称だけで見ても、医療法(第5次改正)、健康保険法などの医療保険各法、老人保健法(高齢者の医療の確保に関する法律へと再編)、介護保険など広範にわたり、まさに保険・医療・福祉の構造を根底から変える規模です。主な事項を並べると、医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直しや地域クリティカルパスの普及の通じた医療機能の分化と連携の推進(脳卒中、がん、小児緊急医療などを重点分野として名指し)、医師不足対策(地域格差、診療科の偏在)、医療法人制度改革、医療費適正化の推進(都道府県の計画策定義務、保険者に対する予防健診などの実施義務などを通じて生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮化をはかり、介護療養型医療施設は廃止する。これらにより医療費抑制をはかる)、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位の保険者の再編・統合、などとなっています。
これらの施策リストを精神科医療のサイドから眺めたとき、私たちはある種の違和感、あるいは不思議な距離感を覚えます。周回遅れのランナーにとって、今般の医療制度改革が遠雷なのか、それとも実は直撃弾なのかが、非常に読み取りにくい状況となっているのです。
例えば、医師不足の問題が論じられるときに小児科や産科ばかりがクローズアップされることは、マンパワーの絶対的不足を制度そのものの問題として長く抱え、昨今では総合病院精神科の危機的状況にも瀕しているわれわれの立場からは、大いなる違和感がああります。また障害者自立支援法の施行以来、精神科医療/福祉という棲み分けの未整理な分野が、都道府県主体の医療と市町村主体の福祉という二極に強引に引き裂かれる事になりましたが、今般の医療制度改革は、そのゆがみを顕在化させる可能性もあります。さらには認知症高齢者の医療と介護の線引きをどこに置くかといったことも、今後の精神科医療の構造を変質させかねない問題です。
こうした情勢下の本紙創刊50号紀念にあたり、私たちの中心課題である精神科医療を、この国の医療体制全体がどこに向かって動こうとしているかという大きな座標軸の中に定位する事を試みます。それによって私たち固有の課題への新たな展望を拓くよすがとなればと思います。